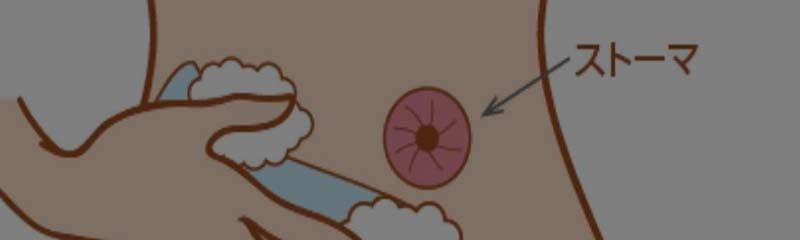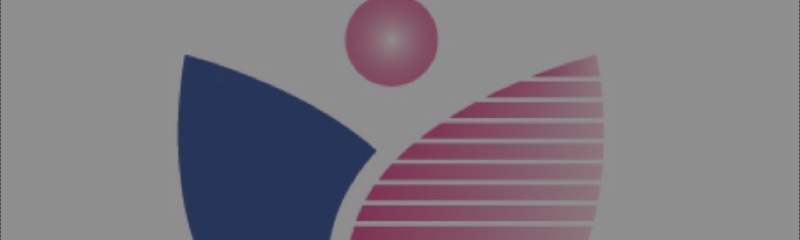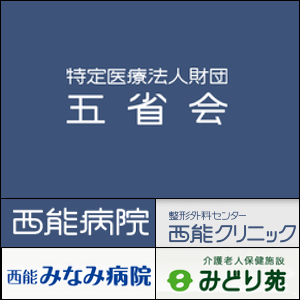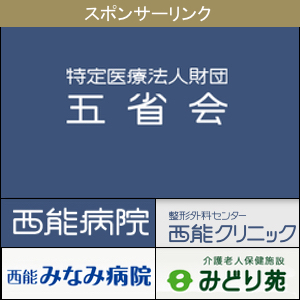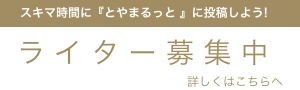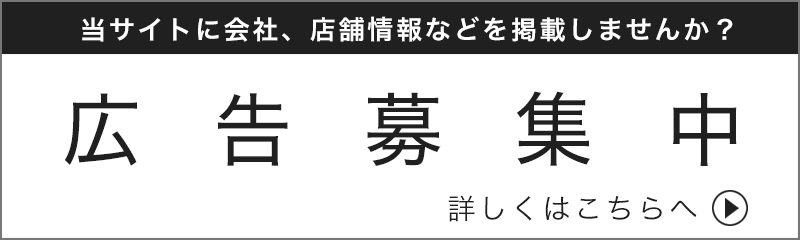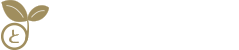『とやまるっと』編集室です。
近年、地球温暖化や異常気象により夏の気温上昇が顕著になっています。
特に高齢者や体力に不安のある方が生活する介護施設では、熱中症は命に関わる深刻な問題です。
こうした状況を踏まえ、2024年4月には労働安全衛生規則が改正され、事業者には「職場の熱中症対策」を講じることが義務づけられました。
今回は、具体的な対策についてもお伝えしていきます!
ぜひ参考にしてください!
----------------------------------------------------------------------------
1. 職場に熱中症対策が義務化された背景
厚生労働省の統計によれば、熱中症による労働災害の発生件数は増加傾向にあり、毎年多くの人が救急搬送され、最悪の場合は死亡に至るケースも報告されています。
こうした状況を受け、2024年4月に労働安全衛生規則(安衛則)の改正が行われ、事業者には「職場における熱中症対策を行うこと」が義務づけられました。
これまでも熱中症対策は努力義務とされてきましたが、猛暑の常態化や働く人々の健康被害の深刻さを踏まえ、法律で明確に義務として定められたのです。
介護施設の場合、この義務化は特に重要です。
理由としては、高齢者は体温調節機能や喉の渇きの感覚が低下しており、熱中症リスクが高いこと。
浴室や調理場、洗濯室などは高温多湿になりやすい環境にあること。入浴介助や移乗介助など身体を使う業務が多く、職員自身も熱中症にかかりやすいことが考えられます。
つまり介護施設では、利用者と職員の双方を守るために、組織的な熱中症対策が不可欠なのです。
2.介護施設で求められる具体的な対策
義務化を受けて、介護施設では以下のような取り組みが実際に必要となります。
環境の整備:各居室や共用スペースの温度・湿度管理、WBGT(暑さ指数)計の設置、エアコン・扇風機・サーキュレーターの適切な利用。
浴室や厨房など高温環境になる場所には換気や冷却対策を強化。
水分・塩分補給の促進:職員は定期的な水分補給を勤務ルールに組み込み、利用者には飲みやすい形での水分提供を徹底。高齢者は「喉の渇きを感じにくい」ため、声かけと見守りが重要です。
勤務シフトの工夫:送迎や屋外作業は気温の低い時間帯に設定し、入浴介助など体力を消耗する業務は交代で行うなど、負担を分散させる仕組みづくりが必要です。
健康チェックと教育:職員は体調チェックシートで日々の状態を確認し、利用者はバイタル測定や表情・発汗などから異常を早期発見。
さらに、全職員が熱中症の初期症状や応急処置を理解しておくことが欠かせません。
3. 自分自身と利用者を守るために
介護現場では「利用者を守る」意識が強調されがちですが、職員自身も同じく熱中症のリスクにさらされています。
体調の異変を感じたら我慢せず休憩を取ること、仲間同士で声を掛け合うことが大切です。
熱中症対策の義務化は決して
「新しい負担」ではなく、働く人と生活する人、双方を守る仕組みの強化です。
現場で働く皆さん一人ひとりが、日々の業務の中で小さな工夫を重ねることが、大きな事故を防ぎ、安心できる介護環境をつくります。
今年の夏からは「自分の体」「同僚の体」「利用者の体」を意識しながら、職場全体での取り組みをさらに強めていきましょう。
情報提供募集!
富山の高齢者・家族・介護者に役立つ情報ポータルサイト『とやまるっと』では、
皆様からの情報提供お待ちしています。
詳しくは、情報提供ページ をご覧ください。
情報お待ちしております!!!
みなさまからの情報で、『とやまるっと』は、育っています。