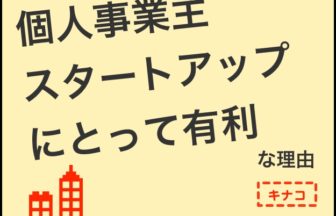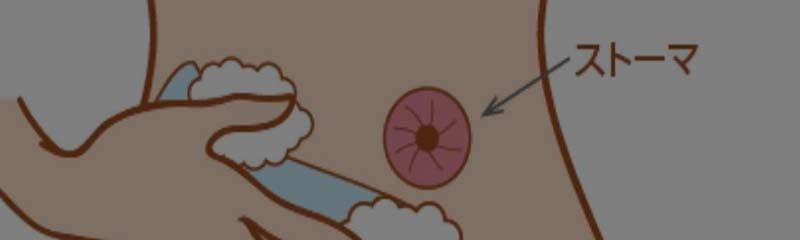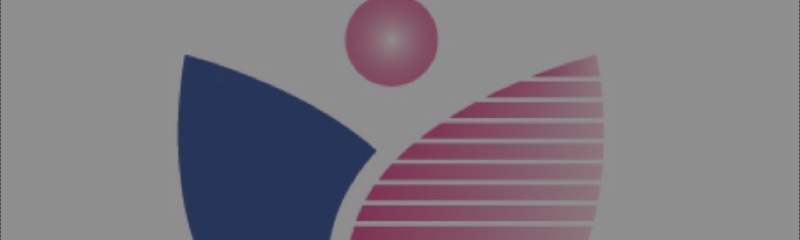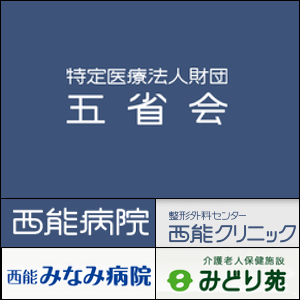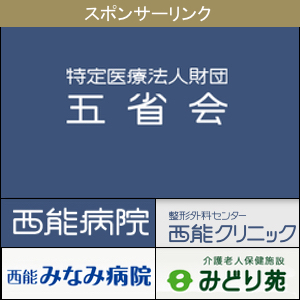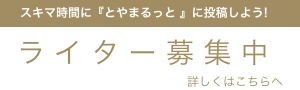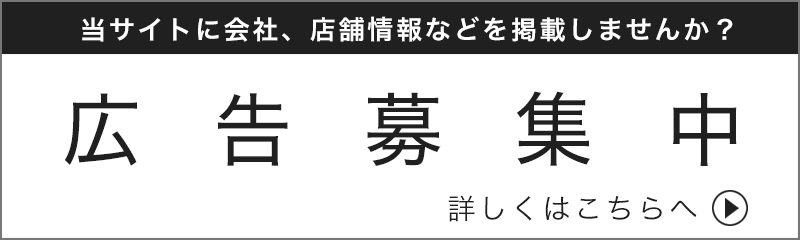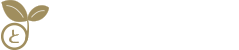『とやまるっと』編集室です。
政府が現在、年収798万円以上の人を対象に社会保険料の引き上げを検討していることが話題になっています。
しかし、「年収798万円以上=高所得者」という認識は妥当なのでしょうか?
また、保険料の引き上げは社会や経済にどのような影響を及ぼすのでしょうか。
本記事では、この問題を多角的に考察して解説します。
ぜひ参考にしてください!
----------------------------------------------------------------------------
1. そもそも年収798万円以上は「高所得者」と言えるのか?
● 統計データから見る「高所得者」像
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」や国税庁の「民間給与実態統計調査」によると、日本の平均年収は約450万円前後(2022年時点)。
年収798万円は、
確かに全体の上位20%程度に位置するため、平均と比べると高い水準にあることは事実
です。
しかし、
「高所得者」と一口に言っても、その実態は住んでいる地域や家族構成によって大きく異なります。
例えば、都市部では家賃や生活費が高く、年収798万円でも可処分所得はそれほど多くないのが現実です。
● 手取り額を考慮すると…
社会保険料や税金を引かれた後の手取り額を見てみると、年収800万円の人の手取りは約600万円前後(扶養状況による)です。
そこから住宅ローンや教育費を支払うと、決して「裕福」とは言えない家庭も少なくありません。
2.社会保険料引き上げがもたらす影響
● 個人の消費行動への影響
社会保険料が上がることで、手取り額が減少し、特に中間層の消費に悪影響を及ぼす可能性があります。
すでに物価上昇や住宅ローン金利の上昇で家計が圧迫されている中、さらに負担が増えると、消費の冷え込みが懸念されます。
● 企業への影響
企業も従業員の社会保険料の一部を負担しているため、保険料の引き上げは企業の人件費増加につながります。
特に中小企業にとっては負担が大きく、賃上げの余力が減る、採用が抑制されるといった副作用が考えられます。
● 税収・社会保障制度への影響
政府としては、社会保険料を増やすことで、財源確保や年金・医療制度の維持を狙っていると考えられます。
しかし、現役世代の負担増は、かえって働く意欲を削ぎ、労働供給の減少や、節税対策の加速につながる可能性があります。
今回の社会保険料の引き上げ議論は、「高所得者とは誰か?」という問題と密接に関係しています。
年収798万円を「高所得者」として一律に負担を求めることが本当に妥当なのか、慎重な議論が必要です。
また、社会保障制度を維持するためには、特定の層に負担を押し付けるのではなく、広く公平な負担の仕組みを検討することが重要です。
社会全体で持続可能な制度をどう構築していくか、今こそ真剣に考える時期ではないでしょうか。
情報提供募集!
富山の高齢者・家族・介護者に役立つ情報ポータルサイト『とやまるっと』では、
皆様からの情報提供お待ちしています。
詳しくは、情報提供ページ をご覧ください。
情報お待ちしております!!!
みなさまからの情報で、『とやまるっと』は、育っています。