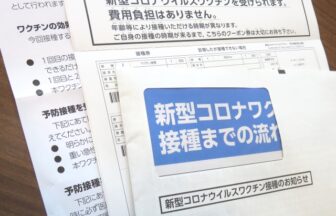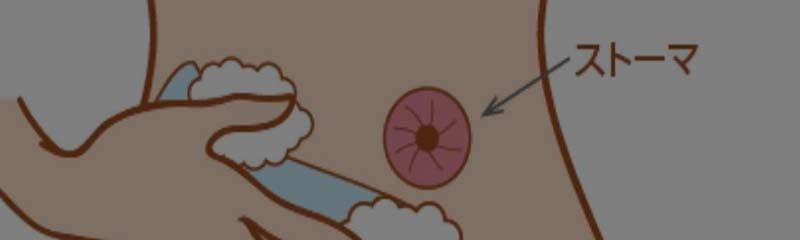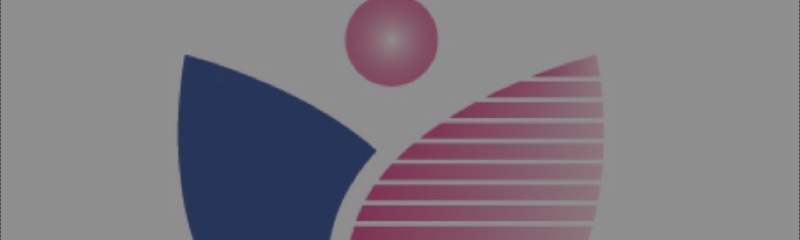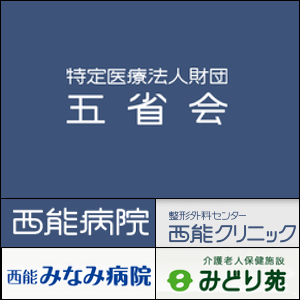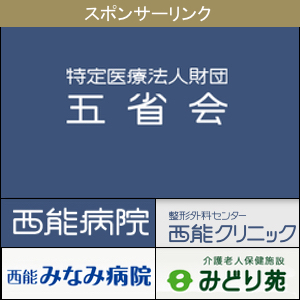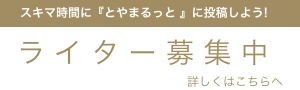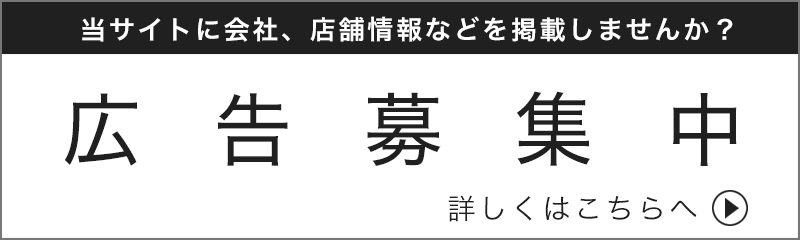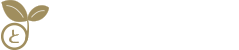『とやまるっと』編集室です。
2025年4月から、育児や介護と仕事を両立する従業員を支援するための制度が大きく変わりました。
これまで企業の努力義務だった取り組みの一部が、事業者にとっての義務として位置づけられたのです。
具体的には、「テレワーク」「短時間勤務」「フレックスタイム」「介護費用の一部補助」など、複数の柔軟な働き方を用意し、従業員が選択できる環境を整備することが求められています。
今回はメリットや意義についても記事にしました。
ぜひ参考にしてください!
----------------------------------------------------------------------------
1. 制度改正の背景と新しい義務
背景には、日本社会の少子高齢化と深刻な介護人材不足があります。
介護職員自身が家族の介護に直面するケースが増え、これまでのように「仕事を辞めて介護に専念する」選択では、人材の流出が避けられません。
こうした状況を改善するため、働き続けながら介護を行える仕組みを整えることが社会的に急務となりました。
2.介護施設で働く人にとっての具体的なメリット
介護職員は肉体的にも精神的にも負担の大きい仕事を担っています。
さらに自宅で親の介護や子育てが重なれば、疲弊して離職に追い込まれることも珍しくありません。
今回の制度改正によって、介護施設で働く人たちには次のようなメリットがあります。
時間の柔軟性が高まる:短時間勤務やフレックスタイムを利用すれば、家族の介護や子どもの送り迎えと仕事を両立しやすくなる。
在宅勤務の選択肢:直接介助が必要な業務は難しいものの、記録の入力やオンライン研修、相談業務など一部業務を在宅で行える仕組みづくりが広がりつつある。
経済的負担の軽減:介護費用補助があれば、デイサービス利用やヘルパー派遣の費用負担を抑えられ、安心して働き続けられる。
つまり、この制度は「辞めるか働くか」という二者択一ではなく、
続けながら支え合う選択肢を広げるものです。
3. 職場全体で取り組む意義
制度が義務化されたとはいえ、実際に活用できるかどうかは職場の理解と協力にかかっています。
介護現場は人手不足が深刻なため、特定の職員がシフトを減らすと残りの職員の負担が増える、という懸念もあります。
そこで重要なのは、職場全体で支え合う文化づくりです。
・管理者は制度の周知と利用しやすい体制を整える
・職員同士は「お互い様」の気持ちで勤務を調整し合う
・利用者や家族にも、制度に基づく職員の働き方を理解してもらう
こうした取り組みを進めることで、職員が安心して働き続けられる環境が生まれます。
結果として離職防止につながり、安定した人員体制のもとで質の高いケアを提供できるようになります。
情報提供募集!
富山の高齢者・家族・介護者に役立つ情報ポータルサイト『とやまるっと』では、
皆様からの情報提供お待ちしています。
詳しくは、情報提供ページ をご覧ください。
情報お待ちしております!!!
みなさまからの情報で、『とやまるっと』は、育っています。